序論
超高齢社会の進展、特に若年層における継続的な低投票率、そして地方自治体が直面する選挙事務の運営負担という民主主義の根幹を揺るがす課題に直面する日本において、選挙制度のデジタルトランスフォーメーション(DX)は喫緊の政策課題として浮上している。特に、デジタル庁の主導する国家的なDX推進の波は、長年議論が停滞していた「電子投票」の実現可能性を巡る議論を再燃させる主要な触媒となっている。
本報告書は、電子投票導入の是非を巡る単純な賛否両論を超え、その実現可能性、内在するリスク、そして導入に向けた戦略的な道筋について、多角的かつ専門的な分析を提供することを目的とする。これにより、より洗練され、証拠に基づいた政策議論の基盤を構築することを目指す。本報告書は、まず電子投票の定義と基本原則を明確にし、日本の過去の導入経緯とその教訓を検証する。次に、導入によって期待される便益と、克服すべき多岐にわたるリスクを包括的に評価する。さらに、海外の先進事例と失敗事例から得られる示唆を抽出し、それを支える技術的基盤を詳述する。最終的に、これらの分析を統合し、日本における電子投票実現のための戦略的なロードマップを提示する。
第1章 電子投票の構造:基本概念と原則
1.1 概念の明確化:投票所電子投票とインターネット投票
電子投票の議論を正確に進めるためには、まず二つの異なる方式を明確に区別する必要がある。
投票所電子投票(電磁的記録式投票)
この方式は、有権者が指定された投票所へ赴き、そこに設置された専用の機械(電磁的記録式投票機)を使用して投票する方法である 1。有権者はタッチパネルなどの画面で候補者を選択し、その一票が電磁的記録媒体に記録される。このシステムの主目的は、開票作業の迅速化と、自書が困難な有権者の投票を容易にすることにある 1。そのプロセスは厳格に管理されており、選挙人名簿との照合、投票機での投票、そして投票データが記録された媒体の開票所への厳重な送致という手順を踏む 2。
インターネット投票
これは、有権者が自身のパーソナルコンピュータ(PC)やスマートフォンなどの端末を利用し、インターネットを介して任意の場所から投票を行う遠隔投票の一形態である 4。この方式は利便性を飛躍的に向上させ、選挙期間中であれば24時間、地理的な制約なく投票を可能にする 6。投票行動に革命的な変化をもたらす可能性を秘める一方で、最も高度なリスクを伴う方式でもある。
1.2 デジタル公共空間:「ネット投票」と「ネット選挙」の区別
一般的に混同されがちな「ネット選挙」と「ネット投票」の概念を区別することは極めて重要である。「ネット選挙」とは、インターネットを利用した選挙運動を指し、日本では2013年に解禁された 8。候補者がウェブサイトやSNS、電子メールなどを通じて有権者に政策を訴える活動がこれにあたる 8。
一方、「ネット投票」は、有権者がインターネットを通じて投票行為そのものを行うシステムを指す 5。両者は共にインターネットを活用するが、法的規制、技術的複雑性、そしてセキュリティ上の含意において根本的に異なる。ネット選挙運動の解禁が、直ちにネット投票の実現可能性や合法性を意味するものではない。
1.3 民主主義原則のデジタル時代への翻訳
公正な選挙の基本原則、すなわち「投票の秘密」「二重投票の防止」「有権者の意思の正確な反映」は、いかなるデジタルシステムにおいても堅持されなければならない 2。
日本の法律は、投票所電子投票機に対して具体的な技術要件を課している。これには、一人の選挙人が二回以上投票することを防ぐ機能、投票者が最終記録前に自身の選択内容を画面で確認できる機能、そして記録データの完全性を保護する措置などが含まれる 2。ここで決定的に重要なのは、法律によってこれらの投票機が
外部の電気通信回線に接続してはならないと定められている点である 10。この規定が、投票所電子投票とインターネット投票を根本的に分離している。
インターネット投票における挑戦は、これらの原則を管理されていない遠隔環境でいかに再現するかにある。これには、有権者のプライバシー(投票者の身元と投票内容の分離)、システムの完全性(ハッキングや改ざんからの保護)、そして公正性(脅迫や買収の防止)の確保が含まれる 4。
この法制度上および概念上の明確な区別は、電子投票に関する議論の最も重要な基礎となる。投票所電子投票は日本において限定的に法制化された現実であるが、インターネット投票は未だ実現していない未来の可能性である。この二つを混同することは、非生産的な政策議論を招く。2002年に制定された「電磁記録投票法」は、地方選挙における投票所での電子投票のみを認めるものであり 2、インターネット投票とは全く異なる。現行法におけるネットワーク接続の禁止規定 10は、両者の間に存在する技術的・思想的な「防火壁」であり、投票所電子投票からインターネット投票への移行が、単なる漸進的な改良ではなく、根本的なパラダイムシフトであることを示唆している。
第2章 日本における電子投票への慎重な挑戦:歴史的・法的レビュー
2.1 2002年特例法:限定的・地域的な権限付与
2002年、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(通称:電磁記録投票法)が施行された 10。これは公職選挙法の特例として制定され、地方公共団体が条例を定めることにより、地方選挙に限定して投票所電子投票を導入することを認めるものであった 1。国政選挙は対象外とされた。日本で最初の導入事例は、同年6月の岡山県新見市であった 12。
2.2 可児市事件:システム障害と信頼失墜のケーススタディ
2003年7月、岐阜県可児市議会議員選挙で、電子投票システムに致命的な障害が発生した。クライアント・サーバー型システムのサーバーに使用されていたMOドライブが過熱し、投票機が長時間にわたりフリーズしたのである 12。この技術的障害により、多くの有権者が投票できずに投票所を去る事態となった。さらに問題を深刻化させたのは、記録された投票数が実際の投票者数を上回るという人為的ミスであった 14。
この選挙結果は提訴され、最終的に名古屋高裁および最高裁によって選挙無効が確定した 12。裁判所は、技術的な欠陥のみならず、待機する有権者に対して正確な情報を提供しなかった選挙管理委員会の運営上の過誤も厳しく指摘した 14。
2.3 その後の「凍結」:10年にわたる停滞の法的・政治的要因
可児市での失敗は、電子投票の普及に冷や水を浴びせた。電子投票条例を制定していた多くの自治体が、条例の凍結または廃止に踏み切った 14。この一件は、単なる技術的な不具合ではなく、デジタル選挙システムの信頼性と管理体制そのものに対する政治的・社会的な信頼を根底から揺るがす「制度的トラウマ」を生んだ。
この信頼の欠如を背景に、2007年と2009年に国政選挙への電子投票導入を目指した法案審議は、政党間の対立や党内の強い反対意見により頓挫した 12。当時の重要な論点の一つは、投票者が自らの投票内容を紙で確認できる「Voter-Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)」の導入を野党側が要求したのに対し、与党連合が反対したことであった 12。2018年の総務省の報告書では、全国の市町村の半数以上が「技術的な信頼性向上」を課題として挙げており、可児市事件が長期にわたる影響を及ぼしたことがうかがえる 14。
2.4 新たな夜明け?デジタル庁と国民的議論の再燃
過去の挫折にもかかわらず、電子投票を巡る議論は再び活発化している。その推進力となっているのは、マイナンバーカードの普及、国民からの強い期待、そしてデジタル庁の主導である 15。河野太郎デジタル大臣は、マイナンバーカードの高い保有率が安全なオンライン本人確認の基盤となり、国民がインターネット投票を「当然の次のステップ」と考えるようになったと指摘している 15。
この動きは政党レベルでも見られ、自民党は特に在外邦人向け投票での導入に「やや賛成」の立場を示し 16、立憲民主党や国民民主党はインターネット投票を可能にする法案を共同提出するなど、具体的な行動を起こしている 4。
近年の議論の再燃は、過去の議論の単なる繰り返しではない。それは、2000年代初頭には存在しなかった「マイナンバーカード」という、政府が保証する標準化されたデジタルID基盤という新たな信頼の柱を前提としている。したがって、現在の議論の成否は、この新しい技術基盤が、可児市事件によって深く刻まれた不信感を克服するに足るものとして、国民および政治家に受け入れられるかどうかにかかっている。
第3章 変革の論理:電子投票がもたらす潜在的便益の分析
3.1 有権者の再エンゲージメント:投票率とアクセシビリティへの影響
利便性と投票率
24時間いつでもどこからでも投票できるインターネット投票は、参加への障壁を劇的に下げる可能性がある。特に、デジタルネイティブでありながら投票率が低い若年層にとって、スマートフォンから数分で投票を完了できる手軽さは、大きなインセンティブとなり得る 6。
高齢者・障害者への配慮
投票所への移動が物理的に困難な人々の投票権を保障することは、電子投票の極めて重要な便益である 6。投票所での電子投票機も、自書が困難な人々にとっては有効な手段となる 1。さらに、ICTを活用することで、視覚障害者向けの音声ガイドや、肢体不自由者向けの簡易な入力インターフェースなど、多様なニーズに対応した投票環境の実現が期待される 11。
外的要因への強靭性
インターネット投票は、台風や豪雪といった自然災害や悪天候が投票率を押し下げたり、投票箱の輸送を妨げたりするリスクを低減する。
3.2 選挙管理の現代化:効率性、迅速性、正確性の向上
迅速かつ正確な開票
電子システムは開票プロセスを自動化し、集計にかかる時間を劇的に短縮すると同時に、人為的ミスを排除する 3。過去の国内での導入事例でも、開票時間が数時間から数分に短縮された実績がある 14。
無効票の撲滅
タッチスクリーンや選択式のインターフェースは、判読不能な「疑問票」や「無効票」の発生を防ぎ、有権者の意思が正確に反映されることを保証する 3。
コスト削減(長期的視点)
初期投資は高額になる可能性があるものの、長期的には投票用紙の印刷、多数の投票所の設営・運営、人手による開票作業などにかかるコストの削減が期待できる。
3.3 海外在住邦人の参政権確保:在外投票問題への解決策
インターネット投票の導入論において、最も説得力があり、緊急性の高いユースケースとして挙げられるのが在外投票である 11。現在、約100万人の有権資格を持つ在外邦人は、投票のために遠方の大使館や総領事館へ赴くか、時間のかかる国際郵便に頼らざるを得ず、投票の機会を逸するケースが少なくない 3。
インターネット投票は、これらの地理的・時間的制約を解消し、彼らが確実かつ簡便に投票権を行使する道を開く 11。この点は河野デジタル大臣も重視しており、在外投票こそが、日本におけるインターネット投票導入の最も論理的で、かつコンセンサスを得やすい出発点であると見なされている 15。
国内の有権者に対する利便性向上も重要だが、それには様々なリスクに関する反論が伴う。しかし、在外投票に関しては、現行制度の欠陥が極めて深刻であるため、インターネット投票がもたらす便益はより明確で、変革への説得力が格段に高い。このため、在外投票を最初の導入対象とすることは、技術的な経験を蓄積し、国民の信頼を醸成する上で、極めて戦略的な一手となり得る。
第4章 リスクの試練:課題の包括的評価
4.1 セキュリティの至上命題:デジタル投票箱を悪意から守る
デジタルシステムは、紙の投票には存在しなかった新たな攻撃経路を生み出す。これには、投票結果を改ざんするハッキング、投票を妨害するサービス妨害(DoS)攻撃、マルウェアの混入などが含まれる 7。有権者の私物端末から中央サーバーに至るまで、通信経路全体の完全性が保証されなければならない 6。システムは、外部からの攻撃だけでなく、悪意ある管理者といった内部の脅威に対しても強靭でなければならない。
4.2 中核的難問:匿名性と監査可能性の両立
これは電子投票における哲学的かつ技術的な根源的課題である。システムは、有権者の身元と投票内容が結びつかないようにする投票の秘密を保証しなければならない 2。同時に、全ての有効な票が正しく集計され、不正な票が加えられていないことを保証するため、システムは
監査可能かつ検証可能でなければならない。
紙の投票では、物理的な投票箱と公開の開票作業によってこの両立が図られる。しかしデジタルシステムでは、この二つの原則が鋭く対立する。もし投票が完全に匿名化されているならば、有権者は「自分の一票」が正しく数えられたことをどうやって確認できるのか。もし確認できるのであれば、それは投票の「受領証」となり、買収や脅迫に利用され、投票の秘密を侵害しないか。
スイスの事例は、このジレンマを鮮明に示している。同国の専門家は、現行技術では「秘密が守られ、再集計が可能で、かつ検証可能な電子投票」は実現不可能だと主張する。プロセスが「ブラックボックス」化し、市民はアルゴリズムを盲目的に信じるしかなくなり、民主主義の信頼基盤が損なわれると警鐘を鳴らしている 19。
4.3 認証の壁:マイナンバーカード、生体認証とその限界
なりすましや二重投票を防ぐための厳格な本人確認は、譲れない要件である。その主要な手段として、公的個人認証サービスを備えたマイナンバーカードが位置づけられている 4。
しかし課題は多い。つくば市での実証実験では、長く複雑な署名用電子証明書のパスワード入力が有権者の離脱を招く大きな障壁となった 20。そのため、より簡易な4桁の利用者証明用パスワードと顔認証を組み合わせる方式に転換された 4。生体認証は利便性が高い一方で、それ自体のセキュリティやプライバシーに関する懸念も存在する 2。
さらに、在外邦人が利用する上で致命的な法的障壁がある。現行制度では、国外に転出するとマイナンバーカードの電子証明書が失効するため、在外投票での利用ができない。これを解決するには法改正が不可欠である。
4.4 社会的側面:デジタルデバイドの克服と国民的信頼の構築
デジタル機器を持たない、あるいは操作に不慣れな人々、特に高齢者が投票権を行使できなくなる「デジタルデバイド」のリスクは深刻である。公衆端末の設置、端末の貸与や購入補助、高齢者向けスマホ教室といった手厚い支援策をセットで講じることが不可欠となる 21。また、従来の紙による投票方法は必ず併用されなければならない 23。
最終的に最も重要かつ脆弱な要素は、国民の信頼である。可児市事件の教訓から、信頼を再構築するには、システムの絶対的な安定性、仕組みの透明性、そして安全性の明確な証明が求められる 24。
4.5 脅迫の脅威:遠隔投票環境における新たなリスク
従来の投票所は、選挙管理者の監視下にあるプライベートな空間を提供し、脅迫や干渉を防ぐ役割を果たしてきた。自宅などから投票するインターネット投票では、この安全装置がなくなる。「家族からの圧力」や、雇用主が従業員に特定の投票を強要するといったリスクが新たに生じる 4。
この問題に対する技術的な解決策として、エストニアで採用されている**再投票(上書き)**機能が提案されている。これは、有権者が投票期間中に何度でも投票し直せる仕組みで、最後に投じられた票のみが有効となる。これにより、脅迫されて投じた票を、後から密かに自身の真の意思で上書きすることが可能になる 4。つくば市での実証実験でもこの機能は実装され、その有効性が確認されている 20。
インターネット投票の最大の障壁は、純粋な技術的問題ではなく、民主主義の基本原則である「秘密性」と「検証可能性」の間に存在する本質的な矛盾という、社会技術的なパラドックスにある。暗号技術などが解決策を提示するものの、その仕組みは一般市民には複雑で不透明に見える。したがって、真の挑戦は、単に安全なシステムを構築すること以上に、そのシステムが専門家でない一般大衆にとって明白に信頼できるものであることをいかにして示すか、という点にある。
第5章 世界の先例:国際的な電子投票の経験から学ぶ
電子投票には単一の国際標準は存在しない。各国の多様なアプローチを比較分析することは、日本の進むべき道を考える上で不可欠な示唆を与える。
5.1 エストニア:「i-Voting」の先駆者とそれを支えるエコシステム
エストニアは、2005年から国政選挙でインターネット投票(i-Voting)を導入している世界的なリーダーである 4。2023年の議会選挙では、史上初めてi-Votingの票数(313,514票)が紙の投票数(301,495票)を上回り、国民生活に深く浸透し、高い信頼を得ていることを示した 26。
主な成功要因:
- 国民皆デジタルID: 義務化され、広く普及した国民IDカード基盤が、安全な本人確認を容易にしている 27。
- 再投票機能: 有権者はオンライン投票を何度でもやり直すことができ、最後に投じた票が有効となる。さらに、投票日に投じられた紙の票は、常にそれ以前のi-Votingを上書きする。これは脅迫への強力な対抗策となる 25。
- 透明性と検証可能性: 投票の秘密は守りつつ、有権者は別の端末(スマートフォンなど)を使って自分の票が正しくサーバーに受理されたかを確認できる 28。システムのソースコードも公開され、公的な精査が可能である 29。
- 技術的アーキテクチャ: 投票者の身元情報(外側の封筒)と暗号化された投票内容(内側の封筒)を分離する「二重封筒方式」という暗号技術を採用し、集計時の匿名性を確保している 29。
5.2 スイス:信頼性と検証可能性を優先した教訓的物語
スイスは高い技術力を持ちながら、深刻なセキュリティと信頼性への懸念から電子投票の導入を停止している 19。専門家や市民活動家は、現行システムでは大規模かつ検知不能な不正を防ぎきれず、同国の直接民主制の根幹を揺るがしかねないと主張した 19。核心的な問題は、意味のある
再集計が不可能であること、そして票が改ざんされていないことを証明できず、市民がシステムを盲信せざるを得ない点にあると指摘された 19。これはエストニアの迅速な導入アプローチとは対照的な教訓を示す。
5.3 米国:断片化された地域ごとのイノベーション
米国での電子投票導入は州や郡レベルで決定され、極めて断片化している。約4分の1の自治体で何らかの電子投票機が使用されている 4。インターネット投票は、ウェストバージニア州やユタ州など一部の州で、主に軍人や在外有権者向けに限定的に利用されており、ブロックチェーン技術を用いたモバイルアプリなどが試されている 4。国家レベルでの統一されたシステムは存在しない。
5.4 韓国:選挙技術の輸出国としての焦点
韓国は、自国の国政選挙でインターネット投票を導入するよりも、選挙技術の開発・輸出国としての側面が強い 4。同国はキルギスに対し、投票所で紙の投票用紙を高速で読み取り集計する**光学式読取機(OCS)**を中核とした「選挙自動化システム」を輸出し、成功を収めた 32。これは電子的に投票するのではなく、
紙の投票用紙の集計を自動化する技術であり、キルギスの選挙の迅速性と信頼性を劇的に向上させた 32。
表5.1 国際的な電子投票システムの比較分析
| 国 | システムの種類 | 導入状況 | 主要な基盤技術 | 特徴的な機能・成果 | 主要な課題・教訓 |
| エストニア | インターネット投票 (i-Voting) | 全国規模(国政選挙) | 国民皆デジタルID | 高い利用率、再投票機能 | 長期的な信頼の維持 |
| スイス | インターネット投票 | 停止・限定的な試行 | 高度な暗号技術 | 国民の信頼を最優先 | 検証可能性のパラドックス |
| 米国 | 投票所電子投票、限定的インターネット投票 | 断片的・部分的 | ブロックチェーン(一部) | 在外有権者向けに利用 | 標準化の欠如 |
| 韓国 | 光学式読取機(技術提供) | 技術輸出 | 光学スキャナ | 開票時間の大幅な短縮 | 真の電子投票とは異なる |
この比較から、電子投票システムの選択は、その国の状況や何を優先するかという戦略的な判断に大きく依存することがわかる。利便性とデジタル化を推進したエストニア、絶対的な検証可能性と信頼を優先したスイス、特定の課題解決に限定して利用する米国など、そのアプローチは多様である。日本の議論は、こうした国際的な文脈の中で自国の優先順位をどこに置くかを問う必要がある。
第6章 安全で信頼されるシステムへの技術的経路
6.1 システムアーキテクチャとそのトレードオフ
スタンドアローン型
各投票機が独立した自己完結型の装置として機能する。データはローカルのリムーバブルメディアに保存され、ネットワークを介さないため、サイバー攻撃のリスクが最小化される 2。
クライアント・サーバー型
投票端末(クライアント)が投票所内のサーバーにローカルエリアネットワーク(LAN)で接続される。可児市事件で障害の原因となったのはこのモデルであり、サーバーが単一障害点(SPOF)となるリスクがある 2。
アーキテクチャの選択は、サーバーモデルの集中管理の効率性と、スタンドアローンモデルの強靭性および分離による安全性との間のトレードオフとなる。
6.2 ブロックチェーンが果たす選挙の完全性確保における役割
ブロックチェーンは、投票記録を改ざん困難な形で記録できる分散型台帳技術である 4。一度記録された票は暗号技術によって前の記録と連鎖するため、後から変更することが極めて難しい 6。つくば市の実証実験では、データの完全性を高めるためにブロックチェーンが活用された 4。この実験からは、基盤となるブロックチェーンの選択が性能に大きく影響することも明らかになった。処理速度を向上させるため、プラットフォームをイーサリアムからハイパーレジャー・ファブリックに変更し、投票処理時間を3-5秒から1-2秒に短縮した 20。
ただし、ブロックチェーンは万能ではない。台帳の完全性は保証するが、本人確認、端末のセキュリティ、匿名性と検証可能性のジレンマといった課題を単独で解決するものではない 6。
6.3 秘密性と検証可能性の鍵を握る高度な暗号技術
暗号技術は電子投票の安全性を支える中核である。
- 暗号化: 投票内容を送信・保管中に保護し、復号鍵を持つ正規の管理者以外が読み取れないようにする 2。
- デジタル署名: 物理的な署名と同様に、投票者の本人性を確認し、投票内容が改ざんされていないことを保証する 2。
- 「二重封筒方式」: エストニアで採用されているこの暗号プロトコルは、投票者の身元情報(デジタル署名付きの「外封筒」)と、匿名の投票内容(暗号化された「内封筒」)を分離する。システムはまず外封筒を検証して不正を防ぎ、その後それを破棄してから匿名の内封筒を復号・集計することで、投票の秘密を保護する 29。
- ゼロ知識証明: 投票内容などの基礎データを一切明かすことなく、集計プロセスなどが正しく行われたことを証明できる先進的な暗号技術 11。理論上、透明性と秘密性の両立問題を解決する一助となる可能性がある 11。
6.4 最前線からの洞察:つくば市の実証実験
つくば市は、複数の実証実験を通じて、日本のインターネット投票における主要な実験場となっている 4。
主な学び:
- 認証の壁は実在する: 初期の実験で用いたマイナンバーカードの長いパスワードは、煩雑すぎて実用的でないことが判明した。顔認証と4桁の暗証番号への転換は、利用者中心の重要な改善であった 20。
- 技術選択の重要性: ブロックチェーン基盤の変更が示すように、性能や拡張性は実用化において重要な検討事項である 20。
- 信頼醸成の重要性: 高校での実験では、投票前にサイバーセキュリティや民主主義プロセスに関する教育ワークショップが実施された。これは、利用者教育が技術そのものと同じくらい重要であることを示唆している 35。
- 透明性は依然として課題: 主催者自身が、システムの「ブラックボックス」性が課題であり、住民に対する透明性の確保が今後の大きなタスクであると認識している。
これらの実証実験から浮かび上がるのは、機能的に安全なインターネット投票システムを構築する技術は概ね存在するものの、真の挑戦は、多様な人々にとって利用しやすく、かつ信頼されるシステムをいかに設計するかという、ユーザーエクスペリエンスと社会工学の領域にあるということである。技術的に安全なだけの解決策(例:長いパスワード)は、ユーザビリティの低さから失敗しうる。したがって、技術開発は、使いやすさ、教育、透明性の確保といった社会的側面と一体で進められるべき、反復的な社会技術的デザインプロセスでなければならない。
第7章 日本における電子投票実現のための戦略的ロードマップ
7.1 基盤となる必須条件:法改正と国民的合意形成
最初のステップは、現行の限定的な2002年法を超えて、インターネット投票を法的に可能にするための公職選挙法改正でなければならない。これは国会(議員立法)の役割であり、超党派の合意形成が求められる 15。同時に、可児市事件の教訓を踏まえ、国民の懸念に応え、幅広いコンセンサスを構築するための透明な国民的議論が不可欠である。
7.2 段階的導入モデル:在外投票からの開始
経験を蓄積し、信頼を醸成するため、段階的かつ漸進的なアプローチを強く推奨する。
- フェーズ1:在外投票。 第3章で論じた通り、これは最も説得力があり、異論の少ない出発点である。現行制度の明確な欠陥に対応するものであり 15、政府の実証実験も既にこの層を対象に行われている 4。
- フェーズ2:限定的な国内適用。 在外投票での成功を受けて、離島の有権者や、入院・長期療養中の有権者など、アクセシビリティが特に大きな課題となっている特定のケースに適用を拡大する。
- フェーズ3:一般提供(選択肢として)。 システムが複数の選挙サイクルを通じて信頼性、安全性、そして国民からの信頼を証明した後に初めて、国内の一般有権者向けの投票オプションとして提供する。その際も、常に従来の紙による投票と併用されなければならない 23。
7.3 エンドツーエンドの信頼フレームワーク:監査、透明性、救済措置
「ブラックボックス」問題を克服するため、システムは信頼を基盤に構築されなければならない。
- 独立した第三者監査: システムのソースコードとハードウェアは、厳格な第三者機関によるセキュリティ監査を受け、その結果は公表されるべきである。
- システムの透明性: 秘密を守りつつも、システムの動作原理は国民に分かりやすく説明されるべきである。エストニアのソースコード公開は、目指すべき高い基準の一つである 29。
- 明確な救済措置: システム障害、ハッキングの疑い、結果への異議申し立てが発生した場合の、明確な法的・手続き的枠組みを事前に整備しておく必要がある。
7.4 デバイドを乗り越える:選挙におけるデジタル包摂国家戦略
インターネット投票の導入は、デジタルデバイドを解消するための強力な国家戦略と一体で進められなければならない。これには、端末購入の補助、無料の公衆Wi-Fiやアクセス端末の整備、そして特に高齢者を対象とした広範なデジタルリテラシー教育(スマホ教室など)が含まれる 21。デジタル投票は、それを利用できない人々を排除する代替手段ではなく、あくまで
追加的な選択肢でなければならない。
7.5 長期的投資のための現実的な費用便益分析
導入には多額の初期費用がかかることを認識する必要がある。2006年の総務省試算では、全国の投票所に投票所電子投票機を全面導入する場合、購入で約1400億円、レンタルで約350億円とされた 37。古いデータではあるが、投資の規模感を示している。現代のインターネット投票システムは異なる費用構造を持つ可能性があり、ある提供事業者の例では初期導入費2000万円、月額保守費用25万円という見積もりもある 38。この費用は、長期的な行政コストの削減、投票参加率向上という無形の価値、そしてデジタル社会における民主主義インフラの現代化という必要性と比較衡量されなければならない。
結論と戦略的提言
本報告書の分析を統合すると、日本における電子投票の実現可能性は、技術的な可否の問題ではなく、政治的な意思、戦略的な実装計画、そして国民的信頼を丹念に構築するプロセスの問題であるという結論に至る。
可児市事件の失敗が残した深い教訓は、いかなる新システムも信頼性と透明性において旧来のものを凌駕しなければならないことを示している。また、スイスの経験は、システムの検証可能性について幅広い合意なしに進むことの危険性を警告している。一方で、信頼されるデジタルIDと利用者中心の機能の上に築かれたエストニアの成功は、目指すべき前向きなモデルを提供する。
以上の分析に基づき、以下の戦略的提言を行う。
- 国会への提言: 在外邦人がマイナンバーカードを国外で利用できるよう関連規制を改正することから始め、インターネット投票の段階的導入を可能にする新法の制定を優先課題とすべきである。
- 政府(デジタル庁・総務省)への提言: 引き続き在外投票のユースケースに研究開発と実証実験を集中させる。いかなるシステム展開の前にも、セキュリティ基準、監査要件、透明性プロトコルを詳述した包括的な「信頼フレームワーク」を策定・公表すべきである。
- 技術提供事業者への提言: 安全性だけでなく、高いユーザビリティと透明性を備えたシステムの開発に注力する。つくば市の実証実験で特定されたユーザーエクスペリエンスの課題を解決するため、政府や市民社会と連携すべきである。
- 市民社会・学術界への提言: 提案されるシステムを独立した立場で精査し、リスクと便益について国民を啓発し、情報に基づいた超党派の国民的議論を促進する上で、極めて重要な役割を果たすべきである。
引用文献
- 第2編 全般的推進状況(平成24年度を中心とした障害者施策の取組) – 内閣府, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h25hakusho/zenbun/h2_05_02_02.html
- 電子投票システムに関する技術的条件 及び解説 – 総務省, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000677452.pdf
- 北米におけるインターネット投票について, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/539.pdf
- R3.9.30WGヒアリング つくば市提出資料 ④公職選挙 … – 地方創生, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/r3/pdf/20210930_shiryou_s_4_1.pdf
- インターネット投票の導入の推進に関する法律案 – 衆議院, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805050.htm
- ブロックチェーンによる電子投票とは?投票におけるブロックチェーンの可能性に迫る, 8月 4, 2025にアクセス、 https://trade-log.io/column/1259
- 【2025年】ネット投票はいつ実現?インターネット投票のメリット・デメリットを徹底解説!, 8月 4, 2025にアクセス、 https://dx-consultant.co.jp/online_voting/
- ネット選挙とは?解禁された背景やメリット・デメリット、できることを解説 – ボネクタ, 8月 4, 2025にアクセス、 https://vonnector.jp/bible/986/
- インターネット選挙運動の解禁に関する情報 – 総務省, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機 …, 8月 4, 2025にアクセス、 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000147/
- ネット投票は実現するのか!?従来の選挙を一変するオンライン選挙の可能性 – wisdom | NEC, 8月 4, 2025にアクセス、 https://wisdom.nec.com/ja/technology/2019032701/index.html
- 電子投票に関する法制度の近時の動向, 8月 4, 2025にアクセス、 https://kiu.repo.nii.ac.jp/record/411/files/KJ00007941339.pdf
- 総務省|電磁的記録式投票制度について – 選挙, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/denjiteki/index.html
- 電子投票について – 総務省, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000547414.pdf
- (考・政治×デジタル)河野デジタル大臣が語る未来の選挙 …, 8月 4, 2025にアクセス、 https://faportal.deloitte.jp/institute/report/articles/001092.html
- [参院選2022]総論賛成、まずは在外投票から―インターネット投票各党の考え方 – 政治山, 8月 4, 2025にアクセス、 https://seijiyama.jp/article/news/nws20220630.html
- 選挙のインターネット投票は、いつできるようになるのか – JAC Recruitment, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.jac-recruitment.jp/market/it/it_topic/d_1608/
- 投票環境の向上方策等に関する研究会 報告(概要) – 総務省, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000568569.pdf
- スイス専門家に聞く ワンクリック投票が危険なワケ – SWI swissinfo.ch, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.swissinfo.ch/jpn/politics/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%8A%95%E7%A5%A8_%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%8F-%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%81%8C%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E3%83%AF%E3%82%B1/45132916
- ブロックチェーン×マイナンバーカード×顔認証技術によるインターネット投票を実施しました! – つくば市, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakuinnovationbudigitalseisakuka/gyomuannai/1/1008320.html
- 行政サービス・電子申請利用の壁「デジタルディバイド」を解消するには?|日本の社会問題, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.glavis-hd.com/social_problem/000154/
- デジ田メニューブック|デジタル田園都市国家構想 – 内閣官房, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/menubook/index.html?h=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%89%E5%AF%BE%E7%AD%96
- インターネット投票の導入の推進に関する法律案 – 衆議院, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405041.htm
- コロナ禍で顕在化した現行選挙制度の課題 ―― ネット投票で「誰一人取り残されない」投票環境の実現を, 8月 4, 2025にアクセス、 https://wisdom.nec.com/ja/feature/government/2022011401/index.html
- 日本ではなぜネット投票が実現しない? エストニアの実践からみえてくるDX推進のカギとは, 8月 4, 2025にアクセス、 https://sakumaga.sakura.ad.jp/entry/2022/11/30/120000
- 議会選で電子投票による票数が制度導入以来初めて過半数に …, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/8ee5825e87733d30.html
- 偶然と党略が生み出したインターネット投票: – researchmap, 8月 4, 2025にアクセス、 https://researchmap.jp/read0141431/published_papers/18983079/attachment_file.pdf
- 2023年、インターネット投票のいま ~コロナ以降のエストニアにおけるインターネット投票, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr411-20230629-mizuno-shikato.html
- 世界のインターネット投票 ~エストニアの選挙法とオンライン投票システム – 情報通信総合研究所, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr397-20220511-mizuno.html
- i-Voting 方式による電子投票選挙とその特長, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.picotec.jp/images/iVoting.pdf
- エストニアのインターネット投票見聞録 1, 8月 4, 2025にアクセス、 https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2008707/files/00680148.pdf
- 韓国電子政府、世界と共有へ(7): 選挙自動化システム : Korea.net …, 8月 4, 2025にアクセス、 https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=144303
- 投票デザインの再構築と ネット投票の可能性 – 杏林大学, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/social_science/research/social-science/pdf/2018vol34no3_kogure.pdf
- 先端技術と民主主義 国際シンポ「日本における電子投票・インターネット投票の未来」 – 政治山, 8月 4, 2025にアクセス、 https://seijiyama.jp/article/news/nws20221114.html
- つくば市が取り組む選挙DX「インターネット投票」実証実験の裏側 …, 8月 4, 2025にアクセス、 https://biz.kddi.com/beconnected/feature/2021/210908/
- 2月7日(金)ネット投票の実験をしました! – 小郡市役所, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/blog/blog/27-3
- 総務省試算 電子投票を全面導入すると国費負担1400億円, 8月 4, 2025にアクセス、 http://maruyama-mitsuhiko.cocolog-nifty.com/security/2006/02/_1400_f6bd.html
- 地方自治体の投票を電子投票システムに変更し効率化と投票率の向上へ – e投票, 8月 4, 2025にアクセス、 https://www.e-tohyo.com/series/municipality/
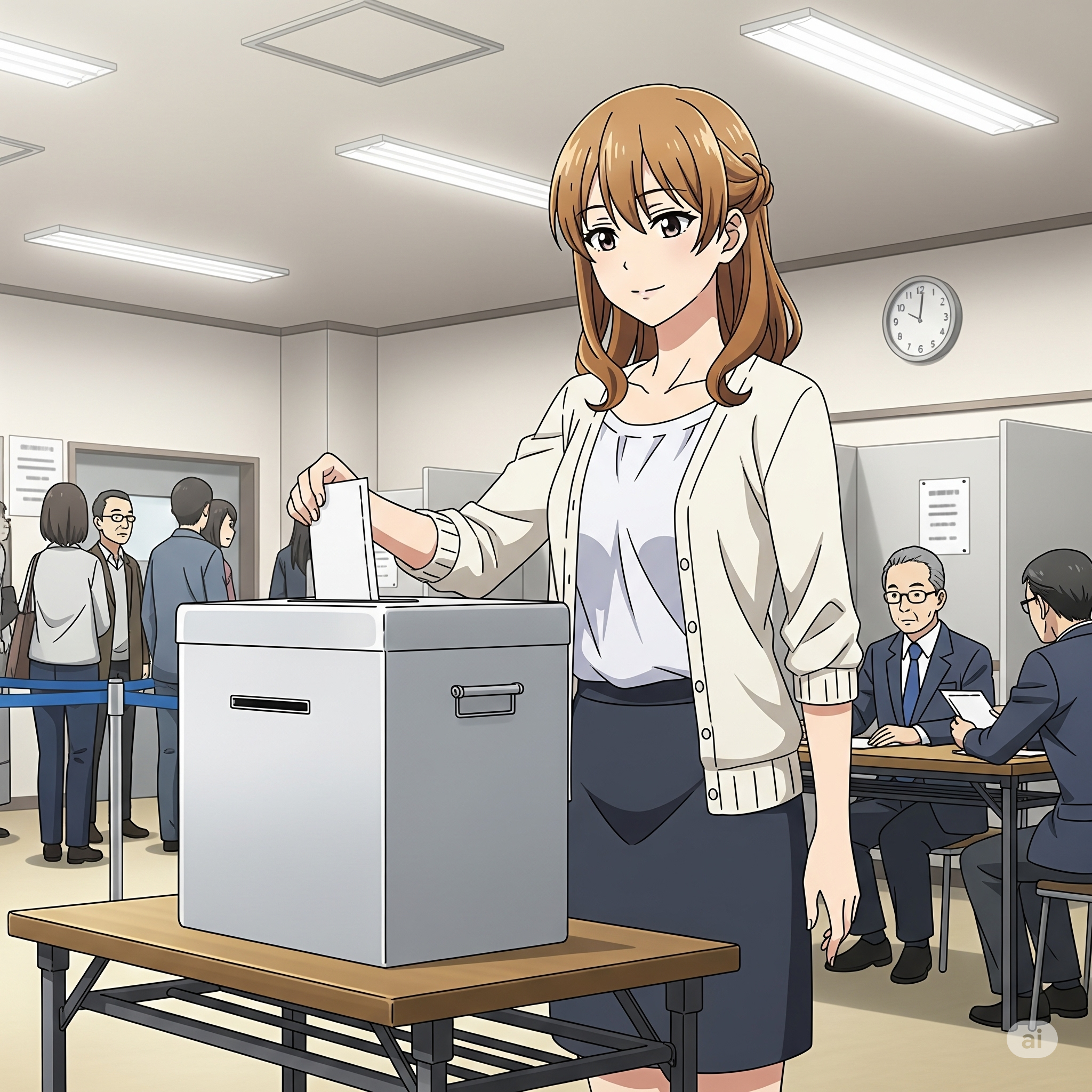

コメント